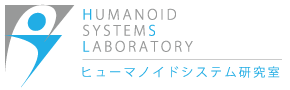玄 相昊について
研究者データベースはこちらをご覧ください。
研究業績
※リストの更新頻度は半年~1年です
- 雑誌論文 (Journal papers)
- 国際会議論文・招待講演 (International conference and invited talk)
- 図書・解説記事 (Books and survey papers)
- 国内学会発表 (Domestic presentation)
履歴
[学歴]- 1998年 3月 早稲田大学 大学院理工学研究科修士課程(機械工学専攻)修了
(修士論文 "2足歩行型ヒューマノイドロボットと人間との物理的インタラクション-手を用いた人間追従歩行―" ) - 2002年 3月 東京工業大学 大学院理工学研究科博士課程(制御工学専攻)修了
(博士論文 "1脚走行ロボットの開発と制御")
- 2002年 4月 東北大学 大学院工学研究科 助手 (機械電子工学専攻)
- 2005年 1月 東北大学 大学院工学研究科 講師 (バイオロボティクス専攻)
- 2005年 4月 ATR 脳情報研究所 研究員
- 2005年 4月 科学技術振興機構 ICORP 計算脳プロジェクト 研究員(2009年3月まで)
- 2008年 4月 ATR 脳情報研究所 BRI研究室 室長代理(2010年3月まで)
- 2009年 4月 情報通信研究機構 未来ICT研究センター バイオICTグループ 専門研究員(2010年3月まで)
- 2010年 4月 立命館大学 理工学部ロボティクス学科 准教授
- 2010年 4月 ATR 脳情報通信総合研究所 脳情報研究所 客員研究員
- 2020年 4月 立命館大学 理工学部ロボティクス学科 教授
研究履歴
研究者のキャリア形成においては、自分が何に興味を持って、主体的にどんな研究を一貫してやっていくのかが重要と思います。私の場合は人型(ヒューマノイド)ロボットに興味を持ちましたが、一か所に長く留まって研究することはできませんでした。しかしそのおかげで様々なチャンスに恵まれたと考えています。
早稲田大学の修士課程ではヒューマノイドロボットで世界的に最も権威のあったラボで学ぶことができました。圧倒されたのはその伝統です。書庫にずらっと並んだ卒修論の数です。当時の早稲田の機械系ラボは何処も大所帯の所謂「体育会系」でしたが、在学生のマインドとして、卒業生の名を汚さないよう頑張って伝統を引き継がなくてはいけないという気持ちが非常に強かったように思います。私は大学院一般入試に背水の陣で臨んだ結果、運よく上位の成績で入れたのですが、そのご褒美として第一希望のチームに配属していただきました。憧れのラボでロボットの研究ができるということで、水を得た魚のごとく、20代前半の若いパワー全開でがむしゃらに知識を詰め込み、戦友と共に徹夜を繰り返しながら、複雑なロボットをみんなで作り上げて動かすという、貴重な経験をさせていただきました。また、学外の協力企業とのやりとりも学びました。自分が立案して実施した最後の1年間の研究は非常に充実したものでした。しかもその仕事は幸運にもIEEEの国際学会の論文賞の最終候補に選ばれ、結果としてラボのブランド維持に貢献できたと思っています。研究者を目指す決定的な機会をいただいた恩師T先生に感謝しています。
東京工業大学の博士課程では制御理論に触れることになります。恩師のM先生はじめ、制御理論の大家のもとに数学が得意で理論が大好きな若手が大勢集まって、日夜レベルの高い議論がなされていました。ドクターとポスドクが多く在籍したラボで、それまで知らなかった概念に触れて言葉を覚えつつの研究生活は易しいものではなく、跳躍走行ロボットの研究を任された機械工学出身の私にとって、孤独で厳しい闘いとなりました。ただ、学位取得が1年遅れた見返りとして、独力で理論を身に着ける習慣を得ることができましたし、他方では、優れたエンジニアM氏と出会って油圧技術に触れることができました。これが現在の大学での研究展開につながります。また、制御と機械の融合がうたわれたプロジェクトが当時進行中で、両分野の文化の違いを目撃できたことも幸運でした。そして何より、最高の伴侶と出会ったことにより、孤独な修行をなんとか乗り越えることができました。
卒業後は内定をいただいた理化学研究所に研究職として働く予定でしたが、T先生からご紹介いただいた東北大学の3年任期付き助教ポストに応募し2002年に着任しました。それまで転々としてきたせいなのか、単に若かったせいなのか、任期というものに関心はなく、一度は大学教員という仕事を経験してみたかったからです。3年後に研究室は解散するということで、ボスのE先生は私に研究室運営のノルマを課さず、その代わり自由を与えてくださいました。その研究室には技官のS氏が常駐されており、学生たちは技官の居るラボ専用のプレハブ実験棟へ息抜きのためによく出入りしていました。関東から東北の広い地域から仙台にやってきた多くの下宿生たちにとって非常に心地よいラボだったと思います。私は買ったばかりの車を実験棟に横付けさせていただき、休日はよく学生たちと釣りやBBQや海に出かけたりしました。自然に囲まれてのびのびと研究できた、非常に密度の高い3年間でした。新婚生活も重なり、人生で最も充実した時間を過ごすことができました。E先生のご配慮に感謝するばかりです。オリジナルな構想で少額ながらも科研費を取り、理論と実験、論文執筆まで完全に一人で成し遂げた喜びは今でも忘れません。ドクター時代に温めていたアイデアで、学外の研究者とネットワークを自ら開拓していった時期でもありました。
次に訪れた転機は研究所への就職です。実は夫婦で米国に飛び出す覚悟をして海外学振に応募したのですが、書類選考で落選してしまいました。そこで改めて国内のポストを探したところ、京都精華町にある株式会社ATRの脳情報研究所でJSTの国際共同研究プロジェクト研究員を公募中でした。そこへタイミング良く応募でき、無事に面接をパスして2005年に着任、修士卒業以来縁が切れていたヒューマノイドロボットの研究に復帰することになりました。驚いたのは、そのロボットが博士課程で苦労して学んだ油圧式だったことです。大きいプロジェクトの中で成果を出していく責任は大変重かったのですが、持てる全てを注ぎ込むに値する仕事でした。御高名なK所長や上司のG氏からは大きな期待を寄せていただき、快適な研究環境で学ばせていただいたことに大変感謝しています。多くの外国人ポスドクが出入りしていたため、英会話力アップというボーナスも付きました。自分としては最初の3年間で多くの結果を残せましたし、若手研究者としての名誉は十分に味わったと考えています。しかしその後の2年間は、米国の巨大テック企業の存在により、心休まる日はあまりなかったと記憶しています。もう少しゆったり構えて周囲とうまく連携できていれば、また違った展開もあったのではないかと振り返るときもあります。
2010年に本学へ准教授として着任しました。優遇されていた環境とポジションを捨てて飛び出すのは早すぎるのではないか?と知人から助言されたのですが、まだ若いうちに、各地で学んできた知識やノウハウを学生に余すことなく伝え、学生と一緒に何か新しいものを作ることに挑戦したいという自分の気持ちに従いました。ゼロからのスタートは予想以上にハードでしたが、いろんな失敗を繰り返しながらも、今まで各地で転々として学んだ知識や経験を活かす形で、学生が努力すれば一流紙に論文を出せる環境を整えることができたと思っています。また、先述のM氏とのご縁で多くの企業のご協力を得ながら実践的な研究教育を展開することができました。
2025年現在、大学に着任後、早くも15年が経ちました。この間、学問を取り巻く(悪いほうへの)環境変化の度合いとスピードはすさまじいものがあり、「研究を通じた教育」の難しさを突き付けられる毎日で、試行錯誤の真っただ中にあります。もちろん本学に限ったことではないと思いますが。どうすれば突破口が見つけられるか?という問題意識が頭の中で大きく占めるようになったと思います。今の仕事が自分の天職だと言えるまでまだまだ時間がかかりそうですが、理想と目標を見失わず、突き付けられた難しいチャレンジをむしろ楽しみながら、自らの本分を果たしていくつもりです。
趣味など
趣味
仕事しながらクラッシックやジャズを聴くのが好きでしたが、最近は全く開拓していません(これまで特に良く聴いたのは交響曲全般とT-Square)。また、好きだった釣りは、子供が生まれて京都に移住してからは(海まで遠いので)諦めました。その代りBBQは続けていて、春のラボBBQで学生達にお肉をふるまっています。最近、有機農業のスクールへ1年間(といっても隔週)通ってみたのですが、とても深い学びがありました。いずれ何かにつながるかもしれません。
今明確に趣味と言えるのは「ITFテコンドー」だけです。大学の頃は部活していましたが、途中で辞めてしまいました。それが心残りで、40歳で道場へ入門して白帯からやり直し、50歳超えにして3段への昇段に挑戦中です。華麗な蹴り技や独特な型はとても難しいですが、難しいほど手に入れたい気持ちが強まりますし、全身を使う組手はとても爽快です。道場の指導を受けながら京都近郊の大学生を対象としたインカレを運営中です。
その他
妻と娘2人の4人で京都市内に居住していますが、私は海が見える田舎への移住をずーーっと夢見ています。
所謂生成AIとは距離を置いています。心の平和を保ちたいからです。とは言っても、スマホを使っている時点で共犯なんですね(笑)。
覇権主義と戦争は止まる気配はなく、世界はますます困ったことになってきました。人類に残された時間はあまり残っていないと思います。
自然の保全と人類の共存共栄のためのチャレンジを応援したいと思います。
2025/09/07