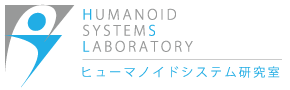見学・配属相談
研究室見学会の案内を随時掲載します。
仮配属に向けた見学会2025
概要
- 実施日時:
10/29(水)16:40~18:15
10/30(木)16:40~18:15
11/5(水)16:40~18:15
11/6(木)16:40~18:15 - 集合場所:
イーストウィング5Fヒューマノイドシステム研究室
見学会の方法
教員が海外研究から戻ったばかりで授業に入っていませんので、最初に教員から40分程度の簡単な自己紹介とプレゼンを行い、その後に、テクノコンプレックスの実験室等を回りながら説明します。また、院生も質問・相談に対応します。
メッセージ
HSLでは単純なものから複雑なものまで、多様なロボットを作って動かしています。理論から実務まで幅広い知識を貪欲に学びたい学生には特に向いています。特に最近はフィールドロボットに関するプロジェクトが複数同時進行中で、外部とのコラボも盛んです。学生はみんなフレンドリーで、互いに教え合いながら個人やチーム課題をクリアし、学会発表も行いながら成長しています。見学相談会では学生メンバーに気軽にいろんな質問をしてしっかり情報を仕入れてください。何はともあれ、まずは学生達が作り上げたロボットシステムの数々を直接ご覧ください。お待ちします。(見学会に来ないで単なる印象や噂だけでラボを選ばないようお願いします)
Q&A
-
制御に興味があります。ロボットを動かせるのでしょうか?
はい、ロボットを動かしていただきます。思い存分です!苦労して学んだ力学や制御の理論がソフトウェアとして実装されるのです。動かないロボット、長時間ただ実験室にぶら下がっているだけのロボットは、それだけで何の価値も生み出さず、むしろレンタルスペースの賃料が無駄になるのですから、粗大ごみよりも有害です(笑)。
しかし、下で述べる通り、ソフトウェアよりもまず、ハードウェアが必要です。ロボットはハードウェアが基本です。卒論ではもっぱらハードウェア設計製作、修論後半でソフトウェア実装と考えてください。テーマや学生の特性によって、ウェイトはやや異なってきますが、どちらも仮説検証という意味では共通しています。
-
どんな学生に向いていますか?
好奇心、熱意、学力、・・・ そんなありきたりの話は省略しますね。
ここでは単刀直入に言いましょう、入口の段階では、ハードウェアを作ることが得意な学生は当研究室に向いていると。メカ設計が好き、3DCADをいじるのが好きな学生は特に向いています。なぜなら、当研究室はロボットを作る研究室だからです。
モノづくりのベースができた学生に対して、教員は機構学や制御理論、その実装方法を教育します。卒論ではもっぱらハードウェア設計製作です、と言いましたが、それは理論に基づいた設計になりますので、設計の過程で各種計算やシミュレーションが伴います。言語はMatlabとPythonを主に使っています。
研究室内では同じチームで「協業」はしますが、「分業」はしません。分業こそが諸悪の根源と確信しているからです。システムの全てを理解し、「ハードもソフトも両方できて当たり前」の学生を育てます。白紙からロボットを設計して動かせる学生を輩出します。したがって学生も教員もとても忙しくなります。
学費は安くはありませんので、もしアルバイトで忙しくなるようであれば、院進は決しておすすめできません。一方、外注も可能な「作業」を研究室内で行う場合(ノウハウ蓄積と教育が目的)、研究費で学生をアルバイト雇用することもよくあります。モノづくりが得意な学生は有利ですね。
-
流行りの強化学習に興味がありますが、使うでしょうか?
必要に応じて導入はしますが、メインテーマでは決してありません。強化学習はロボットを動かすための無数の方法のうちの一つです。PCの速度が速くなり、シミュレータを使った探索が現実的になりました。しかし、Sim2Realがうまく行くとは限りません(Realの部分は我々モノづくりの人間にかかっています)。
派手に動くロボットの動画を見て興味を持つことは理解します。しかし、手段(強化学習)と目的(ロボットをうまく動かす)をはき違えないようにしないといけません。特に、学習で得られたコントローラの構造が理解できないような、強引な方法は有害とすら思っています。計算コストが極端に高い方法は採用しません。もし他の方法でロボットがうまく動くのであれば、強化学習を使うチャンスは無いかも知れません。
今はGPU搭載のパソコンを買えば、誰にも教わらず、顔も合わさず、たった一人でヒューマノイドロボットの強化学習のシミュレーションもできます。しかも、サイズによりますが、自費でヒューマノイドロボットが買えてしまいます。買ってきたロボットをダウンロードしたソフトで動かせるわけです。しかし、それはスマホのゲームとどこが違うのでしょうか?他人が作ったものを「単に使っただけの経験」なら誰にでもできるわけで、そこに価値はないと思っています。
当研究室ではオリジナルなロボットの創造を追求しますので、完成品を買うことはあり得ません。ソフトウェアも基本的なものは自作します。教員は理論も得意ですので、学生が作ったハードウェアに必要な理論とソフトウェア実装の方法を指導します。是非「二刀流」になってください!
なお、博士課程(ドクターコース)へ進学する学生で、自分の研究に強化学習を用いる必要が生じた場合、世界トップクラスの専門家(共同研究者)の指導を受けることができます。
-
自分が作りたいロボットを自由に作れるのでしょうか?費用は負担いただけるのでしょうか?
否です。趣味の自主活動に研究費を投入することは許されていません。研究室は学内にあるAIOLのようなファブラボではなく、研究する場所です。研究を遂行するためにモノづくりが必要というだけです。
研究では新規性が最も重要です。初心者が他人の真似をすることは大事ですし、必要なプロセスですが、それは単なる「お勉強」であって、研究ではありません。研究においては、新規性のないことに時間とお金を費やすことはありません。
また、研究室には大きなビジョンと方法論があります。研究室に所属されている間、学生はそのビジョンや方法論にお付き合いいただきます。その中で、何を作れば社会的価値が生まれるのか?一緒に考えて、チーム内で同意を得ます。研究室と無関係なテーマを単独で研究したい学生はお断りします。
当研究室で行うべき正統性のある研究活動を行います。もちろん費用は全額負担します。その過程でお勉強(単なる知識の吸収)は当然必要ですが、基本的には教科書に書いていない様々なチャレンジ、試行錯誤を経験します。その仮説検証の過程を論文にまとめていただきます。そうしてはじめて単位を取得することができます。
-
就活はできますか? どんな会社に就職していますか?
就活はやっていただかないと困ります^^; 就活の邪魔はしていませんし、学生の自主性を重んじていますのでコアタイムもありません。しかし、研究ミーティングへの出席は必須です。そこで密に研究指導し、成績もシビアに評価するわけですから。
困ったことに、近年、大企業による早期選考付きインターンシップの開始時期が早まっています。もしその波に乗って行こうとする場合、おそらく、卒論からM1の夏休みまでにどれだけ密度高く研究できるか?が勝負になるかと思います。したがって、研究に集中できる時間はもちろん重要ですが、上述したような、研究室との「短期的な相性」は極めて重要になってきます。そのうえで、研究室に配属された直後からM1の夏休みまで1年以上も研究に集中できる「内部進学」生は、就活においても有利になります。正しく努力した結果、何かしらの結果や自信がついてくるわけですから。前倒しで研究して、終活開始までに早めに失敗を経験しておくことは悪くないと思います。就活中にM2での研究を構想しましょう。
当研究室の院生は、ほぼ全員が国内有数の大企業に就職しています(いちいち公開はしません)。偏差値の高い有名国立大学の学生の場合、研究成果よりも前に、既に大学受験を頑張ったという「保証書」があるわけです。それを持たない多くの学生の場合、企業が見ているのは、性格の他には「個人の実力」ということになります。しかしながら、その実力とは一般的な資質であって、個々の研究内容とは全く関係がありません(共同研究先やドクターは例外)。院生の場合、どのような研究内容であれ、大部分の時間を過ごす研究室での取り組み(=研究活動)が学生の一般的な能力向上につながり、そういう学生が企業に選抜されていると言えるでしょう。
また、もし仮に企業が研究室名を見ているとすれば、その研究室の教員が学生を本気でちゃんと教育しているのかどうか、だけと思います。学生による学会発表やその他活動レベルも重要なバロメータでしょう。そういう学生ならば是非引き取って、続きは社内で費用をかけて教育しましょう、となるわけですね。
2025/11/06